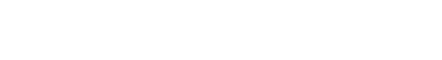【【神様】からの解説】
◎「良賈(りょうこ)は深く蔵して、虚しきが如し」
「君子は盛徳ありて、容貌、愚かなるが如し」
(※『史記・老子伝』・孔子老子会見の場面)
若い孔子は、老子に、
「礼」について、教えをこうた。
しかし、老子は、それには、答えず、
こう、
若い孔子に、警告した。
優秀な商人は、
たとえ、良い品を、仕入れていようと、
常には、蔵の奥深く、隠して、
店頭には、並べたりは、しない。
常には、店頭は、
ガランとさせて、いるものだ。
そして、その品に相応しい、客が、来たとき、
はじめて、その品を、
紹介し、勧めるものだ。
君子と、言われる者は、
たとえ、やれることが、あろうと、
敢えて、やらない。
自らの、力を、誇ったり、
偉そうには、しない、ものだ。
だから、顔つきは、
賢そう、には見えず、
わざと、愚かな、顔つきで、いるものだ。
しかるに、お前(※孔子のこと)は、なんだ。
知っていることを、ひけらかし、
得意気に、自分の考えを、
誰彼なしに、吹聴しようと、している。
肩に力が入りすぎ、
無理が、感じられる。
善意の押し付けは、
もはや、善意では、なくなる。
早く、それに、気づき、
おとなしく、していることだ。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
これを、どう、お前たちは、受け取るであろあか?
老子は、
・傲慢
・独りよがり
・ごり押し
を、強く、戒めているのだ。
まことに、【真理】に、叶ったことである。
いかに、【真理】が、あろうと、
それは、容易には、伝わらない。
それは、受け手の、器、次第だからだ。
・受け手、決定
届け手が、いかに、優秀であろうと、
受け手に、受け取るだけの、器が、なければ、
【真理】は、伝えられない。
受け手の、器、だけしか、
届け手は、注ぐことは、できないのだ。
これを、
・対機説法
(※人を見て、法を説け)
と、言う。
相手の、器に、合わせて、
話は、せよ。
相手、かまわず、
【真理】を、浴びせる、愚行を、
戒めて、いるのである。
受け手に、その気が、生まれ、
聴こう、と、自らし、
そして、器、の分だけ、
蔵の奥から、出してくる。
まことに、それこそ、良賈、では、ないか。
お前も、その、良賈と、なれ。
と、言いたいのである。
今回、は、ここまで、とする。